こんにちは、愉しいを創るコーディスポーツです。
今回は「しっぽ取りゲーム」を紹介します。
「しっぽ取りゲーム」は、幼児や小学生など子どもだけではなく大人まで幅広い年齢層でも愉しめる運動です♪
特別な道具を用意する必要もなく、いろいろとアレンジできるとてもおすすめの運動遊び・レクリエーションのひとつ。屋外、屋内問わずにできるのでぜひ参考にしてみてください。
目次
しっぽ取りゲームとはどんな遊び?
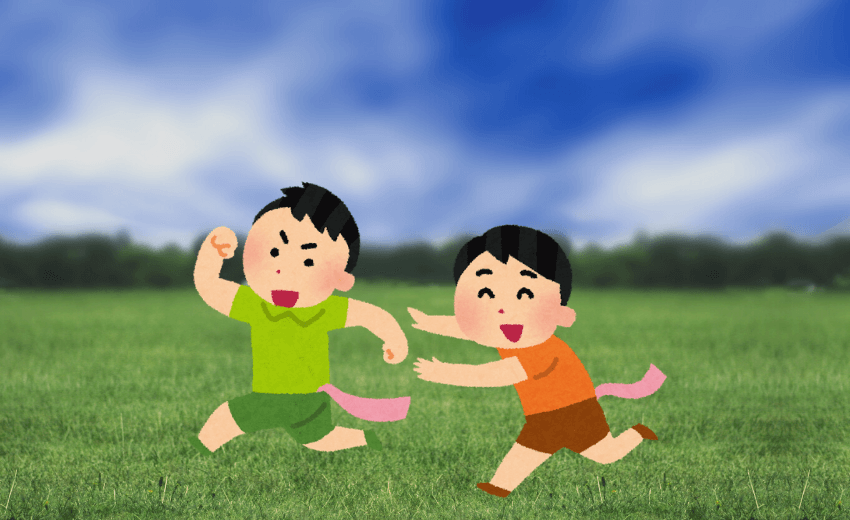
名前のとおり、しっぽを取り合う遊びです。
「しっぽ鬼」とも言われるように、いろいろとある鬼ごっこの種類のひとつ。
個人戦でもチーム戦でも愉しめます。
しっぽ取りゲームで使う道具
下記のとおり「しっぽ」に見立てられそうなものならなんでもOK。
・タオル
・ゼッケン
・ハンカチ
・スズランテープ
・帽子 など
今回紹介する動画の中ではゼッケンを使っていますが、上記に挙げたようなものならどれでも大丈夫です。
あとは、エリアをつくるためのカラーコーンやマーカーコーンがあればバッチリですね。
では、さっそくしっぽ取りゲームを紹介していきます!!
しっぽ取りゲーム【アレンジいろいろ】
今回紹介するのは下記のとおりです。
・しっぽ取りゲーム【4種】
・じゃんけんしっぽ取り
・ネコとネズミ
・ボールも取り入れたしっぽ取りゲーム
では、それぞれ順番に見ていきましょう♪
しっぽ取りゲーム【4種】
室内などせまいスペースでもできるのが、しっぽ取りゲームのいいところ。
1つ目の動画では、4種類の方法を解説していますのでさっそくご覧ください。
〈しっぽ取りゲーム【4種】それぞれの遊び方解説〉
【1】手をつないで1対1(2人でやるしっぽ取り)
①握手をするように手をつなぎます。
②手をつないだ状態のまま、相手のしっぽを取り合います。
注意点として、頭を下げすぎてしまう頭と頭がゴツンとぶつかってしまうので、相手をよく見ながらやるようにしましょう!
【2】縦につながり2対1(3人でやるしっぽ取り)
①2人1組になり、前後に並んだら後ろの人がしっぽをつけて前の人の肩を持つようにします。
②鬼は、2人組の後ろの人がつけているしっぽを取りにいきます。
※2人組の後ろの人は、前の人の肩から手を離さないようにしましょう。
2人組のほうは、前の人を盾がわりにするような形でしっぽを鬼に取られないようにします。
前の人は自分勝手に動いてしまうと後ろの人が離れてしまうので、2人で連動しながら頑張ってしっぽを守りましょう♪
鬼はうまくフェイントを使いながらしっぽを取りに行きましょう!
【3】縦につながり3対1(4人でやるしっぽ取り)
①3人1組になり、1列に並んでそれぞれ前の人の肩を持ちます。いちばん後ろの人がしっぽをつけましょう。
②【2】と同じように、鬼は3人組のいちばん後ろの人がつけているしっぽを取りにいきます。
縦につながる人数が多くなると、しっぽを守る側は他の人と連動して動かないといけないのでその分難易度が上がります。
【4】円になって4対1(5人でやるしっぽ取り)
①4人1組になり、手をつないで円をつくります。1人だけしっぽをつける人を決めましょう。
②つないだ手は離さないように、円のい形をキープしながら鬼からしっぽを取られないように動きましょう。
【2】・【3】と違い、円になる場合は人数をどんどん増やしていくことで、鬼がしっぽを取る難易度が上がりますね。
このようにアレンジの仕方次第で難易度もコントロールできるので、年齢などに応じていろいろと試してみてください^^
また、【2】、【3】、【4】は制限時間をつくって、最後までしっぽを取られなかったらしっぽを守る側の勝ちなどというルールなどをつくっても愉しめます。
しっぽをうまく取るためには、相手をだますための動きを入れたりすることが必要になってくるので、年齢に応じてヒントを出したり、声掛けをしていきましょう。
じゃんけんしっぽ取り
次は、じゃんけんを取り入れたしっぽ取りゲームをご紹介。
サッカーやバスケットボールなどで必要な「切り返しの動き」や「判断力」も鍛えられます♪
〈じゃんけんしっぽ取りの遊び方解説〉
準備として、動画のように10〜15メートルくらいの距離をとってマーカーコーンなどでスタートの位置、エリアを決めておいてください。
3つのパターンを紹介していますが、基本となる動きは下記のとおりです。
①スタートラインからエリアの真ん中あたりまで走っていく。
②真ん中で相手と向き合う位置まできたらじゃんけん。
それでは、それぞれのパターンを解説します。
【パターン1】じゃんけんで勝ったら後ろに逃げる
・じゃんけんで勝った人は、自分のスタート位置に戻るように逃げます。
・じゃんけんで負けた人は、逃げ切られる前にしっぽを取りにいきます。
【パターン2】じゃんけんで勝ったら前に逃げる
・じゃんけんで勝った人は、相手のスタート位置に向かって逃げます。
・じゃんけんで負けた人は、自分のスタート位置に進ませないようにしっぽを取りにいきます。
【パターン3】じゃんけんで負けたら前に逃げる
・【パターン2】とは逆にじゃんけんで負けた人が、相手のスタート位置に向かって逃げます。
・じゃんけんで勝った人は、自分のスタート位置に進ませないようにしっぽを取りにいきます。
このようにじゃんけんの勝敗によってしっぽを取る側を変えたり、逃げる方向を変えたりすることで判断能力も鍛えられます。
前に逃げる場合には、目の前にいる相手をよく見て駆け引きしながらフェイントなどを入れながら動くことも必要になるので、遊びの中で身のこなしも上達していきますね♪
今回は上記の3パターンを紹介しましたが、いろいろとアレンジしてみてください。判断を間違えてしまうこともありますが、気にせずに愉しみながらやっていきましょう!
次に紹介する2つの方法は、動画ではしっぽ取りとして解説していないですが「しっぽ取り」にアレンジ可能なので活用してみてください。
ネコとネズミ
じゃんけんしっぽ取りと同様、10〜15メートルくらいの距離をとってマーカーコーンなどでエリアを決めておいてください。
じゃんけんしっぽ取りとは違い、真ん中からのスタートです。
こちらの動画ではしっぽをつけていませんが、しっぽをつければ「しっぽ取りゲーム」のアレンジ版として使えます。
じゃんけんしっぽ取りのように判断力が鍛えられるだけでなく、聴こえた音に対して素早く反応する能力も鍛えられるのでさまざまな動きの要素も入っていてとてもオススメ!
ボールも取り入れたしっぽ取りゲーム
最後は、ボールも使ってのしっぽ取りゲームのアイデアです。
難易度はかなり上がりますが、ボールを使うことでさらにいろいろな要素が入るので運動神経を鍛えるのにはもってこい♪
動画ではボールを守るだけのゲームを紹介していますが、しっぽもつけてボールを守りつつ、しっぽも守る、または取りにいくというようにしてみても面白いかなと思います。
個人戦、チーム戦でもできるので、ルールをいろいろとアレンジして試してみてください^^
まとめ:しっぽ取りゲームで愉しく運動神経を鍛えよう!
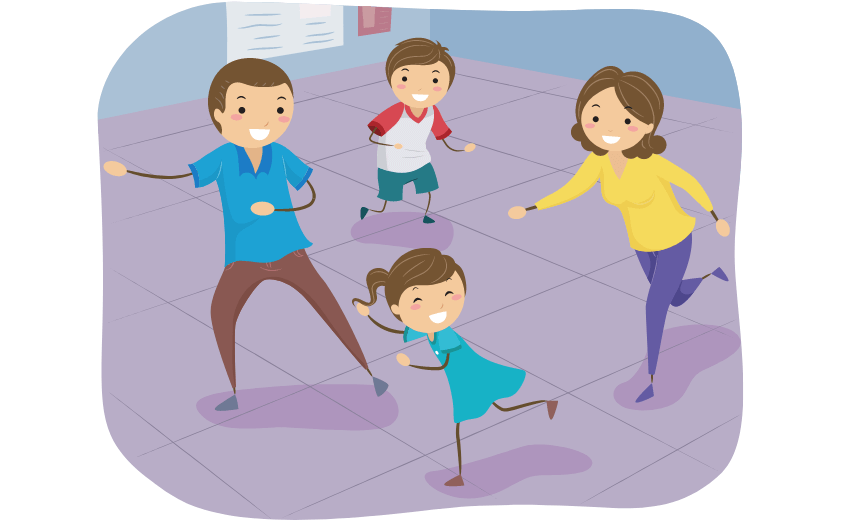
今回は子どもから大人まで愉しめる「しっぽ取り」を紹介しました。
しっぽ取りゲームをアレンジすることで、さまざまなコーディネーション能力が鍛えられます。
たとえば、「反応能力」、「バランス能力」、「変換能力」、「定位能力」、「連結能力」といったものですね。
>>参考:運動神経を鍛える【コーディネーショントレーニング】
ぜひ、年齢に応じてルールを変えたり難易度を変えたりしながら「しっぽ取り」を幼稚園・保育園の運動遊びや学校の体育、またレクリエーションなどに取り入れてみてください♪
■各SNSで情報発信中
各種SNSで情報発信中!
◆YouTube
弊社コーディスポーツのYouTubeチャンネルでは、おうちでもカンタンに運動神経を鍛えられる方法をたっぷり紹介しています。
■書籍情報はこちら
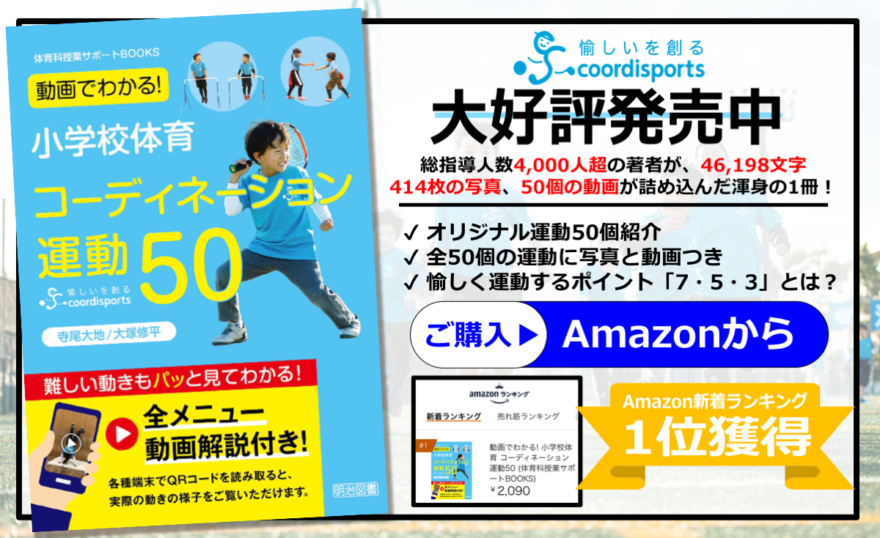


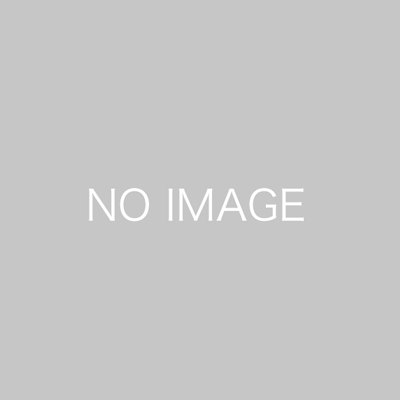
コメント